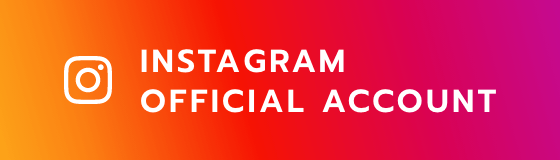COLUMN
お役立ち情報
賃貸オフィス・賃貸事務所に関連する借地借家法の概要

賃貸オフィス・賃貸事務所の利用も物件の賃貸借ですので、借主には借地借家法が適用されます。借地借家法は、借主の立場上の不利を解消するために民法と特別法で制定された法律です。トラブルを未然に防ぐためにも、物件を借りる際には予め押さえておく必要があります。今回は、そんな借地借家法の概要をはじめ、適用範囲や賃料の増減における考え方について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.借地借家法の概要
2.借地借家法の適用範囲
3.賃料の増減額請求における借地借家法の考え方
4.今回のまとめ
借地借家法の概要
借地借家法は、土地・建物の賃貸借において借主を保護する目的で定められる法律です。賃貸借契約を行った際に適用されるもので、民法および特別法にて規定されております。
もともとは借地法と借家法に分かれていましたが、1992年にそれらの統合がなされて誕生しました。当然、借地借家法は賃貸オフィスなどの賃貸借にも適用され、これにより貸主や第三者からの不当な要求に対抗することが可能となるのです。例えば、貸主が第三者に建物を売却し、第三者が立ち退きを要求してきたとしても借主は依然として賃借権を主張することができます。また、建物の売却前に賃貸借契約を行なっていなかった場合でも同様です。
民法においては、契約を交わしていなければ権利の主張ができないものとされていますが、借地借家法では借主の生活を脅かしてしまう観点から権利の主張が行えるものと規定されおり、そちらの効力が優先して発揮される形になります。要するに、民法で定められる規定よりも、特別法である借地借家法の規定のほうがより強く働くのです。
借地借家法の適用範囲
借地借家法には、適用される範囲が存在します。具体的には、無償で賃貸借を行う「使用貸借契約」・建物の一部のみを借りる「間借り」・一時的な使用目的で行う「一時使用目的の建物賃貸借契約」といった契約方法は、いずれも適用範囲外となります。つまり、建物全体やビルのフロアを借りる一般的な賃貸オフィスでは借地借家法が適用されますが、レンタルオフィスのような一部のスペースを借りる形式では適用されません。無論、後者では借主が賃借権を主張することができないため、仮に利用を拒絶された場合はそれに従ってスペースを返還しなければならなくなります。
ちなみに、賃借権には法律によって期限が定められております。民法と特別法で期間は異なり、民法では第604条にて契約内容に関わらず最長50年までとされ、特別法では第29条にて1年未満の期限を設定する場合は期限の定めがないものとし、代わりに30年の期限が設けられることになります。なお、契約で1年以上の期限を設定する場合の際限はありません。また、民法第604条の規定を無効とする内容も定められており、そのうえで規定は特別法が優先されますので、適切な期限が設けられていない場合は借主に30年の賃借権が付与される形になります。
賃料の増減額請求における借地借家法の考え方
賃貸借には、経済的な理由における賃料の増減額請求がつきものです。貸主であれば賃料の増額、借主であれば賃料の減額の要求を提示できます。これらの要求に対する借地借家法における制限はないのでしょうか?
実際には、いずれの要求も借地借家法のもとで認められております。特別法の第32条において、土地・建物の租税や価格の変動、経済事情や周囲の土地・建物の賃料との差が見られるときなどには、契約による制限が設けられていない場合に限り増減額請求が行えるものと定められているのです。なお、契約期間に関係なく要求することができます。
基本的には、貸主と借主の双方の協議による同意で増減はなされますが、協議で決められない場合は裁判を経て判断する形になります。この場合は、裁判期間中に発生した賃料に増減額分の金額に期間分の利子を上乗せし、貸主もしくは借主いずれかが支払うことになります。
今回のまとめ
賃貸オフィスにも、借地借家法は密接に関わってきます。借地借家法は貸主と借主の立場を対等にし、不当な要求にも待ったをかけられる権利を表す法律ですので、賃貸借契約を行う際にはしっかり押さえておくようにしましょう。